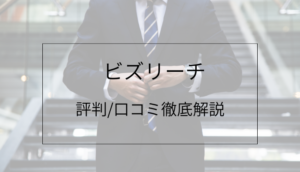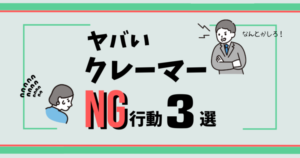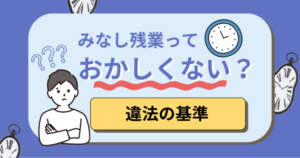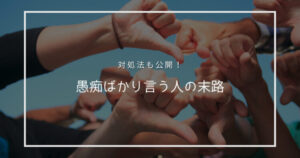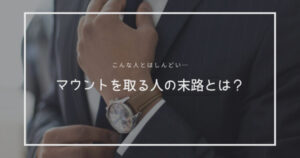- このまま仕事をサボってても大丈夫かな…
- いやいや仕事は要領良くサボってなんぼでしょ!
- でも仕事をサボる人の末路はどんなことになるんだろう?
 けーやん
けーやんあなたもサボっていませんか?
特に生産現場や中小企業に勤めていると、必ずと言っていいほど仕事サボる人に遭遇します。
業務時間内にゲームをしたり、無駄に残業をしたりすることで、周りをイラっとさせているかもしれません。
早速結論からお伝えすると、うまく仕事をサボれる人は優秀なため、どこの企業でも通用します。
そこでこの記事では、仕事をサボる人の特徴や末路について解説していきます。
\ 優秀な人さっさと転職 /
転職満足度No.1!
本記事を読むことでサボる人が優秀だと理解できるようになるので、ぜひ最後まで読んでくださいね。
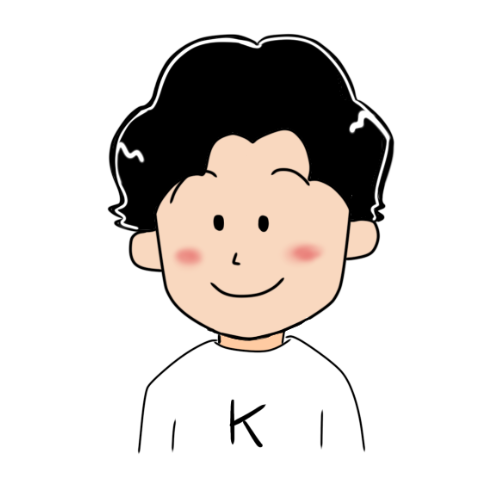
- 高卒のアラフォーで娘2人
- 5度のキャリアチェンジ
- フリーランスから再就職
仕事をサボる人には2パターンある
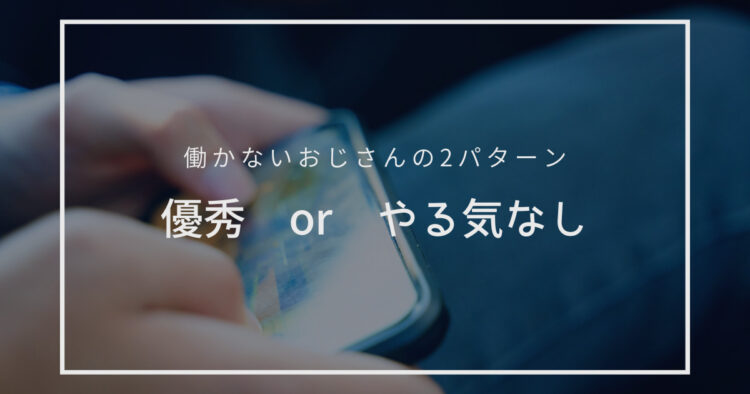
仕事をサボる人には2つの人種が存在しています。
ここでは、どんな種類がのサボる人がいるのかを解説していきます。
仕事を上手にサボる実は優秀な人
仕事をサボる人は、実は優秀な人かもしれません。
彼らは効率的に仕事をこなすために、一見サボっているように見えることがあります。
例えば、三菱地所株式会社では2018年より仮眠制度を導入。
また、インターネット大手GMO株式会社も「おひるねスペース」を設置しています。
昼食後に短時間の仮眠を取ることで、作業効率や生産性の向上につながると期待されています。
このように、仕事をサボる人の中には、実は優秀な人も存在します。
彼らは効率的な仕事をするために、要領よくサボっているのかもしれません。
 けーやん
けーやんこのパターンはすごい人やで!
彼らは後に紹介する、悲惨な末路に陥らずに成功を収めるのではないでしょうか。
単純にやる気の無い人
仕事をサボる人のもう一つのパターンは、単純にやる気の無い人です。
 けーやん
けーやんこっちのパターンがほとんどやで!
やる気が無いことから、どれだけ仕事をせず給料をもらうかに、命をかけていると言ってもいいでしょう。
例えば、業務時間中にスマホでゲームしたり、漫画を読んだりしている働かないおじさんを見たことはありませんか?
 けーやん
けーやん工場勤務時代は酷かったよ。
けど、IT企業に行ってもサボる人はたくさんいたで!
筆者も転職で、製造業からIT業界へと、業界そのものを変えました。
しかし、仕事をサボる人は結局どこにでも生息します。
また、彼らは「仕事はサボってなんぼ」と思っています。
そのため、仕事をサボる人との上手な付き合い方が重要になってくるでしょう。
仕事をサボる人の特徴とは?

実際に仕事をサボる人の特徴はどんなものがあるのでしょうか。
ここでは、さらに細かく仕事をサボる人の特徴について解説していきます。
仕事を上手にサボる効率の良い人
効率の良い人は、仕事サボる人の中でも特徴的な存在です。
彼らは、賢い働き方や独自の方法で効率を追求し、仕事をサボっているように見える場合があります。
仕事をスピーディーにこなし、他人が手間取る作業を短時間で終わらせます。
例えば、職場にこのような人はいませんか?
- サボっているのに、納期をしっかり守っている
- サボっているのに、社内の仕組みに詳しい
- サボっているのに、上の人間に気に入られている
 けーやん
けーやんいるいる!
このように、仕事をサボる人は効率が良く、もしかしたら仕事をサボっているように見えるだけかもしれません。
ただし、彼らの効率的な働き方は、生産性向上に繋がっていることを理解しておくことが大切です。
隠れてサボって上司に良い顔をする人
上司に良い顔をする人は、仕事サボる人の中でも目立つタイプです。
彼らは、上司に対して良い印象を持たせることで、実際の仕事量や成果に関係なく評価されます。
彼らは、コミュニケーション能力や適応力が高く、周囲との人間関係をうまく築けます。
 けーやん
けーやんこれだけで、昇進している人もいるけど、これも能力の一つやね!
しかし、彼らは上司に良い顔をするだけで評価されるため、これが仕事をサボる原因ともなります。
マネジメントをサボる、部下に適当な人
仕事をサボる人は自分の仕事を優先し、部下に対しての指導やフォローが適当な人が多いです。
なぜなら、サボる管理者は自分のことしか考えていないからです。
結果として、部下の成長が阻まれ、組織の生産性が低下する恐れがあります。
 けーやん
けーやん自己中な人ね!
こういう人に遭遇したら、あなた自身の評価も上がらず、昇進が遠のくでしょう。
モチベーションが低い人
仕事をサボる人のタイプの中には、モチベーションが低いために、仕事への取り組みが不十分な人がいます。
この結果、個人のパフォーマンスやチームの生産性に悪影響を与えます。
あなたの職場にもこのような人はいませんか?
- 自分の仕事だけを淡々とこなす人
- 同じミスをしても気にも止めない人
- 周りとのコミュニケーションを取らない人
- 絶対に残業しない人
- 上司に嫌われても気にしていない人
 けーやん
けーやんこれはこれで、メンタル強そうやね
このように、仕事をサボる人にはモチベーションの低いことも特徴として考えらえます。
仕事をサボる人の末路6選

ここからが本題です。
仕事をサボる人の末路について解説していきます。
人が離れていく
仕事をサボる人の末路として、周りの人たちが次第に離れていくことがあります。
これは、サボる人が信頼を失い、コミュニケーションがうまくいかなくなるためです。
 けーやん
けーやん僕がいた工場でも敬遠されてたな〜
彼らは、チームメンバーや上司、部下から信頼を失い、人がだんだんと離れていくでしょう。
陰で悪口を言われる
仕事をサボる人は、陰で悪口を言われることが多いです。
これは、仕事をサボることで他の人に迷惑をかけたり、イラっとさせたりするためです。
あなたの職場にいませんか?
- 「あいつ全然仕事をしない」
- 「給料泥棒だわ」
- 「あいつと給料が同じ(もしくは上)なのは納得いかない」
このような陰口を言われていることでしょう。
 けーやん
けーやん本人が気にしていないことも多いけどね〜
仕事の無い部署に配属される
仕事をサボる人は、組織内での評価が下がり、最終的には仕事の無い部署に配属されることがあります。
 けーやん
けーやんクビにならないだけありがたいな!
仕事をサボる人は、他の人に迷惑をかけるだけでなく、自分自身の業務遂行能力や評価にも影響を与えます。
結果として、組織内での評価が下がり、出世やキャリアアップのチャンスを逃すことになるでしょう。
最悪の場合、仕事の無い部署に配属されることで、キャリアが停滞してしまうことがあります。
しかし、彼らの多くはラッキーと思っていることも少なくありません。
 けーやん
けーやんだって、楽な部署でますます仕事をしなくていいからね
いわゆる窓際社員です。
窓際社員になれれば、ほとんど会社に来るだけで給料がもらえるため、彼らからしたら最高のポストと言えるのではないでしょうか。
しかし、終身雇用が崩壊した現代では、いつリストラや早期退職の候補として挙げられてもおかしくありません。
 けーやん
けーやんビクビクしながら暮らさないといけなくなるで!
新しい仕事についていけなくなる
仕事をサボる人の末路は、新しい仕事についていけなくなります。
理由は明らか、そもそも仕事にやる気がないからです。
時代が進化していく中、会社によっては新しいシステムを導入することもあるでしょう。
あなたの会社にもいませんか?
- パソコンにいつまでも疎い人
- パソコン業務なのに、いつまでもブラインドタッチできない人
- 人差し指でキーボードを打つ人
- マニュアルをいつまでも覚えられない人
 けーやん
けーやん向上心のかけらもないで!
仕事をサボる人は、最終的に仕事自体についていけなくなるでしょう。
年齢次第だが、定年まで逃げ切れる
仕事をサボる人でも、年齢や状況次第で定年まで逃げ切ることが可能な場合があります。
50歳を過ぎると、定年退職までの期間が短くなります。
そのため、窓際社員でも逃げ切れるでしょう。
 けーやん
けーやんあと15年耐え忍んだらリタイアできるもんな〜
終身雇用の崩壊と言えど、まだまだ社員を解雇するのは難しいです。
だからこそ、仕事をサボっていても解雇されにくい状況になります。
しかし、これはあくまで例外であり、仕事をサボることが評価されるわけではありません。
リストラになれば人生詰む
仕事をサボることでスキルが身につかず、リストラの対象になった場合、新たな仕事を見つけるのが難しくなり、人生を詰む可能性が高いです。
彼らは、自己研鑽や新しいスキルを身につける機会を逃し、市場価値が自ずと低くなります。
経済状況や企業の事情によってリストラが行われる際、スキルが不足している人は優先的にリストラ対象となるでしょう。
また、新たな仕事を探す際にも能力不足がネックとなり、転職活動が難しくなることが予想されます。
 けーやん
けーやん定年まで逃げきれなかったら、生活が困窮するやろな〜
実録!筆者が出会った仕事サボる人はこんな人

仕事をサボる人の末路はいかがだったでしょうか。
ここからは、筆者が実際に出会った仕事をサボる人を紹介していきます
業務時間内に体調不良で寝てサボる
ある日、業務に必要なパイプラック(作業台)を上司と一緒に作ることになりました。
作業途中で上司が、
 上司
上司頭が痛い。偏頭痛やわ
と言ってものすごく痛そうでした。
ちょっと休んだら大丈夫と言っていたため、上司には休んでてもらうように促します。
すると、小一時間経っても復活する様子がありません。
そこで、今日は早退して病院に行くか、家で安静にしてもらうように促しましたが、全然帰ろうとしませんでした。
 けーやん
けーやん帰らないことに驚いたね!
よくよく考えたら生産現場でも、このサボる上司はウロウロしているだけで仕事をしているところを見たことがありません。
 けーやん
けーやんサボりの常習者やったな。
無駄に残業してサボる
話の続きです。
偏頭痛で苦しむ上司は、定時になっても帰らず、なんと残業時間も寝て過ごしました。
何度か、帰ることを勧めましたが、それでも彼は帰りません。
そこに意地を感じた僕は、そのまま放置。
無言でパイプラックを仕上げ、その日の業務は終了です。
すると、何事もなかったかのように、
 上司
上司「帰ろか〜」
と、ケロッとしていました。
彼は、何もせずちゃっかりと残業手当をゲットしていたのです。
他の日も彼と仕事をする機会があったのですが、頻繁にタバコを吸いに行ったり、スマホをいじっていたりして、仕事をサボっていました。
 けーやん
けーやんでもめっちゃ出世してたな〜
あの上司は優秀だったのでしょう。
仕事中にスマホゲームをする
なんと仕事中にスマホゲームをしてサボります。
なぜなら僕が勤めていたようなメーカー製造工場は、稼働中に作業員からの呼び出しがなければすることがありません。
 けーやん
けーやん残業しないための事務作業とかはあるけどね。
なんと作業員みんなが汗だくで仕事をする中、クーラーの効いた部屋でポチポチとスマホゲームをしていました。
でも彼はちゃっかりと出世しています。
 けーやん
けーやんやっぱりうまいことサボってて優秀なんやろな〜。
仕事サボる人が取るべき対処法

自分が仕事をサボる人で優秀だと気づいてしまった…。
これからの対処法を解説していきます。
仕事をサボる人は優秀なので、このまま放置
優秀な人は仕事をサボっていても結果を出します。
なぜなら優秀なのだから。
そのため本記事を見なかったことにして、今のまま放置しましょう。
 けーやん
けーやんサボってて給料もらえるなんて、羨ましい…。
転職サイトで今より条件の良い企業へ転職する
仕事をサボる人は優秀なため、転職サイトで今よりも条件の良い企業に転職しましょう。
なぜなら転職活動をすることで市場価値が把握でき、自分がどの企業に通用するのかがわかるから。
優秀ならいつまでも同じ職場に居ないで、少しでも高い年収を目指しましょう。
そこでおすすめの転職サイトならdodaエージェントサービスです。
エージェントがフルサポートしてくれるため、あわよくば転職で年収アップの可能性も。
 けーやん
けーやん求人数が多いから今より条件の良い企業もたくさんあるで!
dodaエージェントサービスの利用は簡単です。
登録は無料で簡単3ステップで転職活動がスタートします。
- 公式サイトにて必要情報を登録
- 職務経歴を入力
- キャリアカウンセリングを受ける
 けーやん
けーやんとりあえず登録してて間違いない
キャリアカウンセリングでは転職の本気度も聞かれるため、思うままに伝えて問題ありません。
今の時代はいつでも転職できるように、自分の市場価値を把握しておくことが必須です。
dodaエージェントサービスに登録して、早めに転職活動を開始しましょう。
そうすることで、より良い職場環境を求めることができるとともに、キャリアアップを図れます。
まとめ 仕事をサボる人は放置か上を目指すかの2択!
いかがでしたか。
今回は仕事をサボる人の特徴や末路、対処法について解説しました。
あなたの職場でも仕事をサボる人に悩まされることがあるでしょう。
しかし、そのような状況に遭遇しても、放置が一番の解決法です。
 けーやん
けーやん他人を変えることはできへん。変えられるのは自分だけやで!
仕事をサボる人に遭遇した場合、自分の仕事に集中し、成果を出して実績と積み上げましょう。
また、仕事をサボる人に耐えられない場合は、転職サイトで自分の市場価値を測ることが賢明です。
転職サイトを利用することで、自分のスキルや経験が市場でどの程度評価されるかを知ることができます。
これにより、自分のキャリアの見直しや今後の選択肢を広げられるのではないでしょうか。
いざ転職したい時にすぐ動けるよう、今のうちから転職活動しておいた方が吉です。
なぜなら、本当に転職したい時には、心身が疲弊していて、転職活動と言ってる場合ではないからです。
以上、最後まで読んでいただきありがとうございました。
\ 転職者満足度No.1 /
仕事サボる人の末路についてよくある質問
- 仕事をサボる人の特徴や共通点は?
-
仕事をサボる人の特徴は、効率が良く、上司に良い顔をして、部下には適当です。また、仕事に対してのモチベーションが著しく低いでしょう。彼らは「仕事はサボってなんぼ」と思っています。
- 仕事をサボる人に対して注意することは効果的ですか?
-
結論からお伝えすると、放置が一番です。注意することで改善が見られる場合もありますが、逆に関係が悪化することの方が可能性が高いです。そのため、注意する前に相手の性格や状況をよく考慮し、上司や他の同僚とも相談することが懸命です。
- 自分の市場価値を測る方法がわかりません。具体的にどうすればいいですか?
-
自分の市場価値を測るためには、転職サイトビズリーチを活用するのがおすすめです。
転職サイトに登録し、自分のスキルや経験を入力、職務経歴書を掲載することで、企業やヘッドハンターからスカウトが来ます。それらの情報を参考にして、自分が市場でどの程度の評価を受けているか把握することができるでしょう。また、業界の動向や求められるスキルのトレンドも把握することで、自分の市場価値をより正確に評価できます。